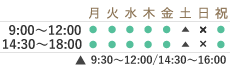小児矯正にかかる医療費控除を徹底解説!申請方法から注意点、よくある質問まで
お子さんの歯並びが気になり、小児矯正を検討しているけれど、費用面が心配…という方はいらっしゃるのではないでしょうか。
高額になりがちな小児矯正費用ですが、実は医療費控除の対象となる場合があり、税金の還付を受け、負担を軽減できる可能性があります。
この記事では、小児矯正にかかる費用で医療費控除を受けるための方法を、2024年最新の情報に基づき徹底解説します。医療費控除の対象となるケース、対象となる費用、申請方法など分かりやすくまとめていますので、ぜひ最後まで読んで、賢く医療費控除を活用してくださいね。
小児矯正と医療費控除の基本

お子様の歯の矯正治療、費用は決して安くありませんよね。そこで活用したいのが医療費控除です。小児矯正にかかる費用の一部が税金から控除される可能性があります。
○そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合、その超えた金額を所得から控除できる制度です。これにより、所得税が軽減され、結果的に納税額が減ったり、払いすぎた税金が還付されたりする可能性があります。家計にとって大きな助けとなる制度です。
医療費控除の対象となる医療費は、自分自身だけでなく、生計を同一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も含まれます。つまり、お子さんの小児矯正費用も、条件を満たせば医療費控除の対象となる可能性があります。
詳しくは国税庁のウェブサイトをご確認ください。
○小児矯正が医療費控除の対象となるケース
小児矯正が医療費控除の対象となるのは、歯列矯正が医療目的で実施された場合です。具体的には、下記のようなケースが該当します。
- 先天的な歯の欠損や形成不全
- 顎変形症(受け口、出っ歯など)
- 外傷による歯の損傷
- 咀嚼(かむこと)や発音に障害がある場合
これらのケースでは、歯列矯正が身体の機能を回復させるための治療と認められるため、医療費控除の対象となります。ただし、単に歯並びを美しくするためだけの審美目的の矯正治療は、医療費控除の対象外となりますので注意が必要です。
なお、子どもの場合歯並びや顎骨の成長を促し、改善させることが目的です。審美目的ではないことが多いため、”医療費控除の対象”となることが期待できます。
判断が難しい場合は、矯正歯科医に相談し、診断書を作成してもらうと良いでしょう。診断書には、矯正治療の目的や必要性が明記されている必要があります。また、領収書も必ず保管しておきましょう。
○小児矯正が医療費控除の対象とならないケース
前述の通り、審美目的の矯正治療は医療費控除の対象外です。具体的には、下記のようなケースが該当します。
- 歯並びの見た目を良くするためだけの矯正
- 芸能活動など、審美性を重視する職業上の理由による矯正
これらのケースでは、矯正治療が医療行為ではなく、美容整形と同様の扱いとみなされるため、医療費控除は適用されません。医療目的か審美目的かの判断は難しい場合もあるため、矯正歯科医との綿密な相談が重要です。
また、マウスピース矯正やワイヤー矯正といった矯正装置の種類によって、医療費控除の可否が変わるわけではありません。あくまで矯正治療の目的が医療目的であるかどうかが判断基準となります。
より詳しい情報は、国税庁の医療費控除に関するパンフレットをご参照ください。
小児矯正の医療費控除で認められる費用

小児矯正において、医療費控除の対象となる費用と対象外となる費用について詳しく解説します。医療費控除を受けるためには、対象となる費用を正しく把握し、領収書などを適切に保管することが重要です。
○医療費控除の対象となる小児矯正費用
一般的に、歯列矯正は医療費控除の対象となりますが、小児矯正の場合は特に「発育段階にある子供の顎の成長を阻害する不正咬合の治療」が対象となります。具体的には、以下のような費用が医療費控除の対象となります。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 検査診断料 | 歯型採取、レントゲン撮影、写真撮影、口腔内検査などの費用 |
| 矯正装置料 | ブラケット、ワイヤー、リテーナーなどの費用 |
| 治療技術料 | 矯正装置の調整、抜歯、外科手術(顎変形症など)などの費用 |
| 再診料 | 定期的な調整や経過観察のための費用 |
顎変形症の手術など、健康保険が適用される治療については、保険適用分は医療費控除の対象となりません。自己負担分のみが対象となりますので注意が必要です。
○医療費控除の対象外となる小児矯正費用
小児矯正において、医療費控除の対象外となる費用は主に以下の通りです。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| ホワイトニング | 歯の漂白を行うための費用 |
| セラミック矯正 (美容目的の場合) |
歯の色や形を整えることを主目的とした矯正費用 |
| 矯正装置の紛失・破損による再作成費用 (故意または重大な過失による場合) |
患者側の責任で矯正装置を紛失または破損した場合の再作成費用 |
| 通院のための交通費 (自家用車の場合) |
公共交通機関を利用した場合の交通費は対象となりますが、自家用車の場合は対象外です。ただし、駐車場代は対象となる場合があります。 |
これらの費用は、美容目的と判断されるか、医療行為に直接関係ないとみなされるため、医療費控除の対象外となります。
○領収書の保管方法と注意点
医療費控除を受けるためには、医療費の支払いを証明する領収書が必須です。領収書は確定申告後5年間は保管しておきましょう。領収書には以下の項目が記載されていることを確認してください。
- 医療機関名
- 患者氏名
- 診療年月日
- 支払金額
また、クレジットカードで支払った場合は、クレジットカードの利用明細書も保管しておきましょう。領収書の再発行は難しい場合もありますので、大切に保管するようにしましょう。
○小児矯正の医療費控除の計算方法
小児矯正にかかった費用が医療費控除の対象となる場合、実際に控除される金額はどのように計算するのでしょうか?医療費控除額の計算方法、計算例、控除限度額について詳しく解説します。
○医療費控除額の計算式
医療費控除額は、以下の計算式で算出します。
医療費控除額 = (年間医療費の合計 - 保険金などで補填される金額) - 10万円(所得金額が200万円未満の場合は所得金額の5%)
年間医療費の合計には、小児矯正の費用だけでなく、病院への通院費や薬代なども含まれます。また、保険金などで補填される金額は、生命保険や健康保険などから受け取った給付金などを指します。
○医療費控除の計算例(小児矯正)
具体的な計算例を見てみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間医療費(小児矯正費用を含む) | 500,000円 |
| 保険金などで補填される金額 | 50,000円 |
| 所得金額 | 4,000,000円 |
この場合、医療費控除額は次のようになります。
医療費控除額 = (500,000円 - 50,000円) - 100,000円 = 350,000円
つまり、350,000円が医療費控除額となり、この金額が所得から控除されます。
○所得金額が200万円未満の場合の計算例
所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく所得金額の5%が控除額の計算に使用されます。例えば、所得金額が150万円で、年間医療費が30万円、保険金等による補填がない場合、医療費控除額は次のようになります。
医療費控除額 = 300,000円 – 150,000円 × 0.05 = 300,000円 – 7,500円 = 292,500円
○控除限度額について
医療費控除には、控除限度額(200万円)が設定されています。年間医療費が200万円を超える場合でも、控除されるのは最大200万円までです。ただし、セルフメディケーション税制の対象となる場合は、一定の要件を満たせば、控除限度額が200万円を超えることもあります。
小児矯正の医療費控除の申請方法

ここでは、小児矯正の医療費控除の申請方法について、確定申告に必要な書類、e-Tax、郵送、還付申告のそれぞれの方法を詳しく解説します。
○確定申告に必要な書類
小児矯正の医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。以下の書類を準備しましょう。
- 確定申告書AまたはB
- 医療費控除の明細書
- 医療費の領収書
- 源泉徴収票(給与所得がある場合)
- 印鑑(認印可)
医療費控除の明細書には、医療機関名、診療年月日、支払金額などを記入します。領収書は原本を保管し、確定申告書には添付しません。税務署から提出を求められる場合があるので、大切に保管しておきましょう。確定申告書AとBのどちらを使用するかは、所得の種類や金額によって異なります。
○e-Taxを使った申請方法
e-Taxを利用すれば、自宅やオフィスからインターネットで確定申告を行うことができます。e-Taxを利用するには、マイナンバーカードまたはICカードリーダライタが必要です。事前に準備しておきましょう。
e-Taxのメリットは、24時間いつでも手続きができること、税務署への来訪が不要なこと、還付金が早く受け取れることなどが挙げられます。
○郵送による申請方法
確定申告書を作成し、必要書類を添付して税務署に郵送する方法もあります。郵送の場合は、配達記録郵便など、配達の記録が残る方法で送付することをおすすめします。
提出先は、納税地を管轄する税務署です。
○還付申告について
還付申告とは、納めすぎた税金を取り戻すための手続きです。医療費控除によって税金の還付を受ける場合は、還付申告を行います。還付申告は、確定申告と同じように、e-Taxまたは郵送で行うことができます。
還付申告ができるのは、過去5年分までです。還付申告の期限が過ぎている場合は、税金の還付を受けることができませんので注意しましょう。
以上の情報を参考に、自分に合った方法で小児矯正の医療費控除の申請を行いましょう。
小児矯正の医療費控除に関するよくある質問
ここでは、小児矯正の医療費控除に関するよくある質問にお答えします。
Q.矯正装置の種類によって医療費控除額は変わる?
A.いいえ、変わりません。医療費控除の対象となるのは、治療にかかった費用です。矯正装置の種類(ブラケット、マウスピース型装置など)や材質(金属、セラミックなど)の違いによって控除額が変わることはありません。あくまで治療目的であることが重要です。ただし、治療目的でない審美目的の矯正治療は医療費控除の対象外となります。
Q.部分矯正でも医療費控除は受けられる?
A.はい、受けられます。部分矯正であっても、歯列矯正が医療行為として認められるものであれば医療費控除の対象となります。ただし、前歯など一部の歯のみを審美目的で矯正した場合は、医療費控除の対象外となります。治療目的であることを証明するために、医師の診断書が必要となる場合もあります。
Q.医療費控除の申請期限は?
A.医療費控除は、医療費を支払った年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行うことで申請できます。還付申告の場合は、5年間遡って申請が可能です。
Q.複数の病院で小児矯正を受けた場合の医療費控除はどうなる?
A.複数の病院で小児矯正を受けた場合でも、それぞれの病院で支払った医療費を合算して医療費控除を申請できます。それぞれの病院から受け取った領収書を保管し、確定申告の際に添付してください。
Q.小児矯正と合わせて受けた、抜歯や虫歯治療などの費用も医療費控除の対象になる?
A.はい、小児矯正に直接関連する抜歯や虫歯治療などの費用も医療費控除の対象になります。矯正治療中に行った歯のクリーニングや定期検診なども対象となる場合があります。領収書は大切に保管しておきましょう。
Q.子どもの歯並びが悪く、コンプレックスを抱えている。心理的なケアも医療費控除の対象になる?
A.歯並びの悪さが原因で心理的なケアを受けた場合、その治療が歯列矯正と直接関連している場合は医療費控除の対象となる可能性があります。ただし、医師の診断書や治療内容の詳細な説明が必要となる場合もありますので、事前に税務署や税理士に相談することをお勧めします。
Q.医療費控除を受けるための領収書はどうやって保管すればいい?
A.領収書は、医療費を支払った年度ごとにまとめて保管することをお勧めします。領収書を紛失した場合に備えて、コピーを取っておいたり、電子データで保存しておくのも良いでしょう。国税庁のウェブサイトでは、領収書の記載事項に関する詳細な情報が提供されています。
Q.クレジットカードで小児矯正の費用を支払った場合、医療費控除は受けられる?
A.はい、受けられます。クレジットカードで支払った場合でも、医療費を支払ったとみなされます。クレジットカード会社から発行される利用明細書ではなく、医療機関から発行される領収書が必要となりますので、大切に保管してください。
| 医療費の種類 | 医療費控除の対象 |
|---|---|
| 小児矯正治療費 | 対象 |
| 矯正装置代 | 対象 |
| 抜歯費用(矯正治療に関連するもの) | 対象 |
| 虫歯治療費(矯正治療に関連するもの) | 対象 |
| 定期検診費用(矯正治療中) | 対象となる場合あり |
| ホワイトニング | 対象外(審美目的のため) |
上記は一般的なケースであり、個別の状況によって判断が異なる場合があります。疑問点がある場合は、税務署または税理士に相談することをお勧めします。
まとめ
この記事では、小児矯正にかかる費用と医療費控除について詳しく解説しました。小児矯正は、歯並びや噛み合わせの改善を目的とした医療行為であり、一定の条件を満たせば医療費控除の対象となります。装置の種類や部分矯正か全体矯正かなどは関係なく、医療行為と認められれば控除を受けられます。
医療費控除を受けるためには、領収書の保管が必須です。また、確定申告の際に必要な書類を揃え、e-Taxまたは郵送で申請を行うことができます。医療費控除の適用期間や子供の年齢なども考慮し、正しく申請を行いましょう。
この記事が、小児矯正の医療費控除について理解を深める一助となれば幸いです。
小児矯正で顎を広げる!ベストな時期・最新の治療法・料金を徹底解説
お子様の顎が狭くて心配していませんか?
今回は、小児矯正で顎を広げることによるメリット・デメリット、ベストな時期、最新の治療法、費用相場、注意点などを徹底解説します。
顎が狭いことで起こる見た目や健康への影響、床矯正・マウスピース矯正・急速拡大装置といった治療法ごとの特徴や費用、治療期間の違いなどを詳しく説明することで、お子様に最適な治療法を選択するための判断材料を提供します。さらに、信頼できる歯科医院の選び方や治療中のケア、定期検診の重要性といった、小児矯正を成功させるためのポイントも網羅。
よくある質問にもお答えしているので、小児矯正に関する疑問を解消し、お子様の健やかな成長をサポートするための情報が満載です!
小児矯正で顎を広げるメリット

顎が狭いと、見た目や健康面に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。小児矯正で顎を広げることで、これらの問題を未然に防ぎ、健やかな成長をサポートすることができます。
見た目への影響の改善
顎が狭いことで、口元が後退して見えたり、顔が歪んで見えたりすることがあります。小児矯正で顎を広げることで、顔のバランスが整い、より調和のとれた美しい顔立ちへと導くことができます。特に成長期のお子供様の場合、顎の成長を促すことで、将来的な顔貌の改善に大きく貢献します。
口元の後退の改善
顎が狭いことで、下顎が上顎に対して後退しているように見えることがあります。これを「反対咬合」や「受け口」と呼びます。小児矯正によって顎を広げることで、下顎の位置を改善し、バランスの良い口元を作ることができます。
顔の歪みの改善
顎の左右の成長に差があると、顔が非対称になり、歪んで見えることがあります。小児矯正で顎を広げることで、左右の顎のバランスを整え、顔の歪みを改善することができます。
健康面への影響の改善
顎が狭いことは、見た目だけでなく、健康面にも様々な影響を及ぼします。小児矯正で顎を広げることで、これらの問題を改善し、健やかな成長を促すことができます。
歯並びの改善
顎が狭いと、歯が並ぶスペースが不足し、歯並びが悪くなることがあります。叢生(そうせい:歯が重なって生える状態)や乱杭歯(歯がガタガタに生えている状態)は、顎の狭さが原因となることが多いです。小児矯正で顎を広げることで、歯が綺麗に並ぶためのスペースを確保し、歯並びの改善を図ることができます。綺麗な歯並びは、虫歯や歯周病の予防にも繋がります。
呼吸の改善
顎が狭いと、気道が狭くなり、口呼吸になりやすい傾向があります。口呼吸は、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。小児矯正で顎を広げることで、気道を広げ、鼻呼吸を促すことができます。鼻呼吸は、空気中のウイルスや細菌をろ過する機能があり、風邪や感染症の予防に役立ちます。また、鼻呼吸は、睡眠の質の向上にも繋がります。
発音の改善
顎が狭いと、舌の位置が不安定になり、正しい発音がしにくくなることがあります。特にサ行、タ行、ナ行、ラ行の発音が不明瞭になることがあります。小児矯正で顎を広げることで、舌の動きをスムーズにし、発音の改善をサポートすることができます。
咀嚼機能の向上
顎が狭いと、食べ物をしっかりと噛み砕くことが難しくなり、消化不良の原因となることがあります。小児矯正で顎を広げることで、咀嚼機能を向上させ、消化を助けることができます。しっかり噛むことで、脳の発達にも良い影響を与えます。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防
顎が狭いと、気道が狭くなり、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のリスクが高まります。小児矯正で顎を広げることで、気道を確保し、SASの予防に繋がることがあります。特に、いびきや睡眠中の無呼吸が気になる場合は、専門医に相談することをお勧めします。
顎が狭いことによるデメリット

顎が狭いことは、見た目だけでなく健康面にも様々な悪影響を及ぼす可能性があります。将来的な問題を防ぐためにも、顎が狭いことによるデメリットを正しく理解しておくことが重要です。
見た目への影響
顎が狭いことで、顔全体のバランスが崩れ、以下のような見た目への影響が現れる可能性があります。
- 顔が小さく見える
顎が狭いことで、相対的に顔が小さく見え、幼い印象を与えてしまうことがあります。 - 口元が出ているように見える
顎が後退していることで、口元が前方に出ているように見え、横顔の印象に影響が出ることがあります。 - Eラインが崩れる
Eラインとは、鼻先と顎先を結んだラインのことです。顎が後退していると、Eラインが崩れ、美しい横顔の条件から外れてしまう可能性があります。 - 下顎が二重あごに見える
顎が狭いことで、あごの下に脂肪がつきやすく、二重あごに見えてしまうことがあります。
健康面への影響
顎が狭いことは、見た目だけでなく、以下のような健康面への影響も懸念されます。
- 歯並びの悪化
顎が狭いと歯が並ぶスペースが不足し、歯並びが悪くなる可能性が高くなります。叢生(そうせい:歯が重なり合って生えること)や乱杭歯(らんぐいば:歯が不規則に生えている状態)などの不正咬合のリスクが高まります。 - 咀嚼機能の低下
歯並びが悪くなると、食べ物をしっかり噛み砕くことができなくなり、咀嚼機能が低下します。消化不良や胃腸への負担につながる可能性があります。 - 発音障害
歯並びや顎の位置は、発音にも影響します。顎が狭いと、サ行やタ行などが発音しにくくなることがあります。 - 呼吸の問題
顎が狭いと気道が狭くなり、口呼吸になりやすくなります。口呼吸は、口内乾燥や歯周病、虫歯のリスクを高めるだけでなく、免疫力の低下やアレルギー症状の悪化にもつながる可能性があります。また、睡眠時無呼吸症候群のリスクを高めるという報告もあります。 - 顎関節症
顎の関節に負担がかかり、顎関節症を引き起こす可能性があります。顎関節症は、顎の痛みや開口障害、関節雑音などの症状を引き起こします。
小児矯正で顎を広げるベストな時期

顎の成長を利用して効率的に顎を広げるためには、小児矯正を始める時期が重要です。お子様の歯の生え変わり時期を考慮し、最適なタイミングで治療を開始することで、より効果的な結果を得ることができます。大きく分けて、乳歯期、混合歯列期、永久歯列期の3つの時期に分けて解説します。
乳歯期(3歳〜6歳頃)
乳歯が生え揃う3歳〜6歳頃は、顎の骨が柔らかく、成長も活発な時期です。この時期に顎の狭さや不正咬合の兆候が見られる場合は、早期治療を開始することで、後の永久歯の歯並びや顎の成長に良い影響を与える可能性があります。この時期の矯正は、主に顎の成長を促すことを目的とし、取り外し可能な装置を使用することが一般的です。指しゃぶりや舌突出などの癖の改善もこの時期に行うことで、顎の発達を正常な方向へ導くことができます。
この時期に適応される主な装置としては、床矯正があります。床矯正は、取り外し可能な装置で、顎の成長を阻害する原因を取り除き、正常な発達を促します。また、筋機能訓練も併用することで、より効果的な治療が期待できます。
混合歯列期(6歳〜12歳頃)
乳歯と永久歯が混在する6歳〜12歳頃は、顎の成長がピークを迎える時期です。この時期は、顎の骨がまだ柔らかく、矯正治療による歯の移動や顎の拡大が比較的容易に行えます。そのため、顎の狭さを改善するだけでなく、歯並びの乱れも同時に治療することが可能です。
この時期に適応される主な装置としては、床矯正、急速拡大装置、マウスピース矯正などがあります。急速拡大装置は、短期間で顎の幅を広げることができる装置で、上顎の骨の縫合部分を利用して拡大を行います。マウスピース矯正は、透明なマウスピース型の装置を用いるため、目立ちにくく、取り外しも可能です。
| 装置 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 床矯正 | 取り外し可能、顎の成長促進 | 装着時間が必要 |
| 急速拡大装置 | 短期間で効果的 | 痛みを伴う場合がある |
| マウスピース矯正 | 目立ちにくい、取り外し可能 | 適応症例が限られる |
それぞれの装置にはメリット・デメリットがあるため、お子様の歯並びや顎の状態、生活習慣などを考慮して、最適な装置を選択することが重要です。
永久歯列期(12歳以降)
永久歯が生え揃う12歳以降は、顎の成長が緩やかになり、骨も硬くなってきます。そのため、小児期に比べて歯の移動や顎の拡大に時間がかかる傾向があります。しかし、顎の成長が完全に止まっているわけではないため、適切な治療を行えば、顎を広げることは可能です。
この時期に適応される主な装置としては、ワイヤー矯正、マウスピース矯正などがあります。
ワイヤー矯正は、ブラケットと呼ばれる装置を歯に取り付け、ワイヤーで歯を動かしていく方法です。
マウスピース矯正は、永久歯列期でも使用可能な場合があり、透明なマウスピースを交換しながら歯並びを整えていきます。
永久歯列期での顎を広げる治療は、難易度が高くなる場合があるため、日本歯科医師会の認定医などの専門医に相談することが重要です。
どの時期に矯正治療を開始するかは、お子様の歯並びや顎の状態、成長段階によって異なります。そのため、歯科医師による適切な診断と治療計画の立案が不可欠です。気になることがあれば、早めに歯科医院を受診し、相談することをおすすめします。
小児矯正の治療法
顎の狭窄は、見た目だけでなく、呼吸や発音、咀嚼などにも影響を及ぼす可能性があります。小児期における適切な矯正治療は、健やかな成長発育のために非常に重要です。ここでは、小児矯正の治療法を詳しく解説します。
床矯正
床矯正の種類と特徴
床矯正は、取り外し可能な装置を用いて顎の成長を促し、歯並びを整える治療法です。主に乳歯列期から混合歯列期にかけて適用されます。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
|
拡大床 |
ネジを回すことで装置を広げ、顎骨の成長を促進します。 |
| 機能訓練装置 | 舌や口周りの筋肉のトレーニングを促し、顎の正常な発達を促します。代表的なものとして、ムーシールドやツインブロックなどがあります。 |
| 保定装置 | 歯列矯正後の後戻りを防ぐために使用されます。 |
床矯正のメリット・デメリット
メリット |
デメリット |
|---|---|
| 取り外し可能で、口腔内の清掃がしやすい | 装着時間をきちんと守らないと効果が出にくい |
| 比較的費用が安い | 適用できる症例が限られる |
| 顎の成長を促すことができる | 装置の紛失や破損のリスクがある |
マウスピース矯正
マウスピース矯正の種類と特徴
マウスピース矯正は、透明なマウスピース型の装置を装着することで歯を少しずつ動かしていく治療法です。取り外し可能で、目立ちにくいのが特徴です。近年、小児矯正にも適用されるようになってきています。
インビザライン・ファーストのような子供向けのマウスピース矯正も登場しています。従来のマウスピース矯正と比較して、顎の成長をより効果的に促すように設計されています。
マウスピース矯正のメリット・デメリット
メリット |
デメリット |
|---|---|
| 透明で目立ちにくい | 装着時間をきちんと守らないと効果が出にくい |
| 取り外し可能で、口腔内の清掃がしやすい | 適用できる症例が限られる |
| 金属アレルギーの心配がない | 費用が比較的高額 |
急速拡大装置
急速拡大装置の種類と特徴
急速拡大装置は、上顎の骨を短期間で広げるための固定式の装置です。主に上顎の幅が狭い場合に用いられます。ネジを毎日一定回数回すことで、上顎骨の正中口蓋縫合を広げます。
代表的な急速拡大装置としては、ハイラックスやバイダーなどが挙げられます。
急速拡大装置のメリット・デメリット
メリット |
デメリット |
|---|---|
| 短期間で顎の幅を広げることができる | 発音や食事に一時的な影響が出る場合がある |
| 外科手術を回避できる場合がある | 装置が目立つ |
| 後戻りが少ない | 痛みを伴う場合がある |
小児矯正で顎を広げる治療期間
小児矯正で顎を広げるための治療期間は、使用する装置の種類、お子様の年齢や顎の成長具合、そして目指す矯正の程度によって大きく異なります。一般的には、数ヶ月から数年かかる場合もあり、一概に「〇ヶ月で終わる」とは言えません。そのため、治療開始前に歯科医師としっかり相談し、治療計画を立てていくことが重要です。治療期間が長くなる可能性もあるため、保護者の方の理解と協力も不可欠です。
治療法による期間の違い
治療法によって、治療期間は大きく変わります。以下に主要な治療法と、それぞれのおおよその治療期間をまとめました。
治療法 |
期間 |
特徴 |
|---|---|---|
| 床矯正 | 1~3年 |
顎の成長を利用して顎を広げるため、比較的時間がかかります。 |
| マウスピース矯正 | 1~2年 | 歯の移動に重点を置いた治療法で、顎の拡大効果は限定的です。症例によっては床矯正などと併用する場合もあります。 |
| 急速拡大装置 | 3~6ヶ月 | 短期間で顎の骨を拡大させる装置ですが、後戻りを防ぐために保定期間が必要です。 |
小児矯正の費用相場
小児矯正の費用は、使用する装置の種類や治療期間、治療を受ける歯科医院によって大きく異なります。費用の目安を把握し、治療計画を立てる際の参考にしてください。
治療法別の費用相場
治療法 |
費用相場 |
備考 |
|---|---|---|
| 床矯正 | 20万円~50万円 | 比較的安価な治療法ですが、治療期間が長くなる場合があります。 |
| マウスピース矯正 | 40万円~80万円 | 取り外し可能なため、食事や歯磨きの際に便利です。透明なマウスピースを使用するため、目立ちにくいというメリットもあります。 |
| 急速拡大装置 | 10万円~20万円 | 短期間で顎を広げることができますが、適応症例が限られます。 |
装置の種類別の費用相場
装置の種類 |
費用相場 |
備考 |
|---|---|---|
| 床矯正装置 | 装置代込みで20万円~50万円 | ネジを回して顎を徐々に広げていく装置です。 |
| マウスピース型矯正装置(インビザラインなど) | 40万円~80万円 |
透明なマウスピースを定期的に交換しながら歯を動かしていきます。 |
| 急速拡大装置(クワドヘリックス、ハイラックスなど) | 10万円~20万円 | 短期間で上顎を拡大する装置です。 |
| バイオネーター | 10万円~20万円 | 下顎の成長を促進する装置です。 |
| チンキャップ | 無料~数万円 (床矯正などと併用されることが多い) | 下顎の過成長を抑える装置です。 |
上記の費用はあくまで目安であり、歯科医院によって異なる場合があります。 実際の費用については、歯科医院で相談してください。
小児矯正を受ける上での注意点

小児矯正は子供の将来の歯並びや顎の成長に大きく影響するため、慎重に進める必要があります。信頼できる歯科医院選びから治療中のケア、治療後の定期検診まで、様々な注意点があります。しっかりと理解した上で治療を始めましょう。
信頼できる歯科医院選び
小児矯正を成功させるためには、経験豊富で信頼できる歯科医師を選ぶことが非常に重要です。以下のポイントを参考に、最適な歯科医院を見つけましょう。
- ・日本矯正歯科学会の認定医であるか
- ・小児矯正の実績が豊富であるか
- ・治療方針や費用について丁寧に説明してくれるか
- ・セカンドオピニオンを受け付けているか
- ・通院しやすい場所にあるか
複数の歯科医院を比較検討し、お子様と保護者にとって最適な医院を選びましょう。口コミサイトや知人の紹介なども参考にすることができます。
治療中のケア
小児矯正中は、毎日の丁寧なブラッシングが欠かせません。装置が付いているため、食べカスが詰まりやすく、虫歯や歯周病のリスクが高まります。歯科医師の指導に従い、正しいブラッシング方法を身につけましょう。
ケア用品 |
使用方法 |
効果 |
|---|---|---|
| 歯ブラシ | 矯正装置専用の歯ブラシや、毛先の細い歯ブラシを使用する | 装置の隙間や歯の表面を効果的に清掃 |
| 歯間ブラシ | 装置と歯の隙間、歯と歯の間の清掃 | 食べカスやプラークの除去 |
| デンタルフロス | 歯と歯の間の清掃 | 歯間ブラシでは届かない細かい部分のプラーク除去 |
| 洗口液 | ブラッシング後に使用 | 口臭予防、虫歯予防 |
定期的な歯科医院でのクリーニングも重要です。専門家によるクリーニングで、家庭では落としきれない汚れを除去し、口腔内を清潔に保ちましょう。
食事の注意点
矯正装置を破損する可能性のある、硬い食べ物や粘着性の強い食べ物は控えましょう。キャラメルやガム、せんべいなどは注意が必要です。また、飴やチョコレートなどの糖分の多いお菓子も虫歯のリスクを高めるため、摂取量に気をつけましょう。
定期検診の重要性
小児矯正は、治療が完了した後も定期検診を受けることが大切です。歯並びや噛み合わせの状態をチェックし、後戻りを防ぎます。また、虫歯や歯周病の早期発見にも繋がります。歯科医師の指示に従い、定期的に検診を受け、健康な歯を維持しましょう。成長に伴う変化にも対応できるため、顎の成長が止まるまで継続的に観察することが推奨されます。
保定装置の使用についても、歯科医師の指示に従い、正しく使用することで後戻りを防ぎ、美しい歯並びを維持することができます。疑問点や不安なことは、遠慮なく歯科医師に相談しましょう。
まとめ
この記事では、小児矯正で顎を広げるメリット・デメリット、ベストな時期、最新の治療法、費用相場、注意点などについて解説しました。顎が狭いことによる見た目や健康への影響を理解し、お子様の歯並びや顎の発達に不安を感じたら、早めに矯正歯科に相談することが大切です。
信頼できる歯科医院選びや治療中のケア、定期検診も重要です。疑問や不安があれば、遠慮なく歯科医師に相談し、納得した上で治療を開始しましょう。
小児矯正は、お子様の将来の健康な歯並びと美しい笑顔のために大切な投資です。この記事が、お子様の矯正治療を検討する上で少しでもお役に立てれば幸いです。
【小児矯正】意味ない?と迷う前に知っておきたい!成功させるためのポイントと注意点
「小児矯正って意味ないの?」と疑問に思っていませんか?
実は、小児矯正の必要性は、お子様の歯並びの状態や顎の成長具合によって大きく異なります。この記事では、小児矯正が本当に意味がないケース、逆に効果的なケースを具体的に解説し、メリット・デメリット、種類ごとの費用相場、成功させるためのポイントや注意点まで、網羅的にご紹介します。
ぜひお子様の歯並びに関する親御さまのお悩み解決に役立ててくださいね。
小児矯正って意味ないの?よくある誤解と真実

「小児矯正って意味ないんじゃないの?」そう思っている親御さんもいるかもしれません。確かに、子どもの歯並びはまだ成長過程にあり、自然に改善する可能性もあります。しかし、だからといって全ての場合で小児矯正が不要というわけではありません。小児矯正の必要性は、顎の成長や歯並びの状態、そしてお子さんの生活習慣など、様々な要因によって異なります。
本当に意味ないケースとは?
小児矯正は万能ではなく、必ずしも必要とは限りません。以下のようなケースでは、すぐに小児矯正を始める必要はなく、経過観察となる場合もあります。
顎の成長による自然改善が見込める場合
乳歯から永久歯に生え変わる時期は、顎の骨も成長し、歯並びが自然に改善されることがあります。特に、顎の成長が十分に見込まれる場合は、急いで小児矯正をする必要はないかもしれません。定期的な歯科検診で経過観察を行い、必要に応じて矯正治療を検討します。ただし、顎の成長には個人差があるため、専門医の判断が重要です。
軽度の歯並びの乱れの場合
軽度の歯並びの乱れ、例えば、歯と歯の間に少し隙間がある、歯が少しだけ重なっているといった程度であれば、必ずしも小児矯正が必要とは限りません。成長とともに自然に改善する可能性もありますし、永久歯が生え揃ってから矯正治療を行う方が効率的な場合もあります。しかし、軽度であっても、不正咬合の種類によっては早期の介入が必要なケースもあります。例えば、反対咬合(受け口)などは、放置すると顎の成長に悪影響を及ぼす可能性があるため、早期の治療が推奨されます。
小児矯正が効果的なケースとは?
一方で、以下のようなケースでは、小児矯正が非常に効果的です。早期に治療を開始することで、将来的な大掛かりな矯正治療を回避できる可能性が高まります。
顎の成長に問題がある場合
上顎前突(出っ歯)、下顎前突(受け口)、反対咬合、開咬など、顎の成長に問題がある場合は、小児矯正によって顎の成長をコントロールし、正常な発達を促すことができます。特に、顎の成長が活発な時期に矯正治療を行うことで、より効果的な改善が期待できます。早期に治療を開始することで、外科手術が必要なケースを回避できる可能性も高まります。
重度の歯並びの乱れの場合
歯が重なり合っている、歯が大きく傾いている、歯がねじれているなど、重度の歯並びの乱れがある場合は、小児矯正によって歯並びを整えることができます。重度の歯並びの乱れは、虫歯や歯周病のリスクを高めるだけでなく、発音や咀嚼にも影響を与える可能性があります。
悪習癖の改善を促す場合
指しゃぶり、舌突出癖、口呼吸などの悪習癖は、歯並びの乱れの原因となることがあります。小児矯正では、これらの悪習癖を改善するための装置を使用することもあります。悪習癖を早期に改善することで、歯並びの悪化を防ぎ、正常な顎の成長を促すことができます。
| ケース | 小児矯正の必要性 |
|---|---|
| 顎の成長による自然改善が見込める | 経過観察 |
| 軽度の歯並びの乱れ | ケースバイケース |
| 顎の成長に問題がある | 必要 |
| 重度の歯並びの乱れ | 必要 |
| 悪習癖の改善 | 必要 |
小児矯正のメリットとデメリット

小児矯正には、成人矯正にはないメリットがある一方で、デメリットも存在します。どちらにもしっかりと目を向け、お子様にとって最適な選択をすることが重要です。
小児矯正のメリット
小児矯正のメリットは、顎の骨の成長を利用できることにあります。これにより、成人矯正では難しい様々な改善が可能になります。
永久歯を抜歯せずに矯正できる可能性が高まる
顎の成長をコントロールすることで、歯が生えるスペースを確保しやすくなり、永久歯を抜歯せずに矯正できる可能性が高まります。抜歯を避けられることは、歯の健康維持という観点からも大きなメリットです。
顎の成長をコントロールできる
小児期は顎の骨がまだ成長段階にあるため、矯正装置によって顎の成長をコントロールすることができます。これにより、受け口や出っ歯などの不正咬合を改善しやすくなります。 成長を利用することで、骨格的な問題の改善も期待できます。
顔のバランスを整える
顎の成長をコントロールすることで、顔全体のバランスを整える効果も期待できます。美しい口元だけでなく、より調和のとれた顔立ちへと導きます。
コンプレックスの解消
歯並びの悪さは、子ども心に大きなコンプレックスとなる場合があります。小児矯正によって歯並びが改善されれば、自分に自信を持つことができ、積極的な性格へと変わる可能性も期待できます。また、発音の改善にもつながる場合があります。
虫歯や歯周病のリスク軽減
歯並びが整うことで、歯磨きがしやすくなり、虫歯や歯周病のリスクを軽減することができます。将来的な口腔内の健康維持にも繋がります。
小児矯正のデメリット
メリットが多い小児矯正ですが、デメリットも存在します。事前に理解しておくことで、よりスムーズに治療を進めることができます。
治療期間が長くなる場合がある
小児矯正は顎の成長に合わせて治療を進めるため、治療期間が長くなる場合があります。永久歯が生え揃うまで数年かかるケースも珍しくありません。また、子どもの成長速度には個人差があるため、治療期間も一概には言えません。
費用がかかる
小児矯正は自由診療となるため、健康保険が適用されず、費用がかかります。装置の種類や治療期間、医療機関によって費用は異なりますが、数十万円かかるのが一般的です。分割払いやデンタルローンを利用できる医療機関もありますので、事前に確認しておきましょう。
子どもの協力が必要
小児矯正は、子どもの協力なしには成功しません。装置の装着や取り外し、食事や歯磨きなど、日常生活における様々な場面で子供の協力が必要です。保護者の方のサポートも不可欠です。
後戻りの可能性
小児矯正後も、顎の成長や舌の癖、生活習慣などによって後戻りが起こる可能性があります。後戻りを防ぐためには、保定装置の使用や定期的な検診が重要です。矯正後のケアも重要です。
装置による違和感
矯正装置を装着することにより、発音しづらくなったり、口の中に違和感を感じたりすることがあります。装置の種類によっては、痛みを伴う場合もあります。慣れるまでは時間がかかるかもしれません。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 費用 | — | 保険適用外のため高額になる場合がある |
| 期間 | 顎の成長を利用できる | 長期にわたる場合がある |
| 抜歯 | 抜歯の可能性が低い | — |
| 後戻り | — | 後戻りの可能性がある |
| その他 |
|
|
小児矯正のメリット・デメリット、費用についてより詳しく知りたい方は、公益社団法人 日本歯科医師会のウェブサイトも参考にしてください。
小児矯正の注意点

小児矯正は、大人の矯正治療とは異なり、顎の成長を利用しながら歯並びを整えていくため、いくつかの注意点があります。治療を始める前に、これらの注意点をしっかりと理解しておくことが重要です。
年齢と成長段階に合わせた治療計画
小児矯正は、子供の年齢や成長段階に合わせて適切な治療計画を立てる必要があります。顎の成長が活発な時期に行うことで、より効果的な矯正治療が可能になります。思春期早発症などの場合は、成長のタイミングを慎重に見極める必要があります。また、永久歯の生え変わり時期なども考慮しながら、最適な治療法を選択することが重要です。
後戻りの可能性と対策
小児矯正は、治療後も後戻りする可能性があります。特に、顎の成長が完了していない時期に矯正治療を終えた場合、後戻りが起こりやすい傾向があります。後戻りを防ぐためには、保定装置(リテーナー)を指示された期間、きちんと装着することが非常に重要です。リテーナーの種類や装着期間は、症例によって異なりますので、矯正歯科医の指示に従ってください。また、舌の癖や指しゃぶりなどの習慣がある場合は、これらの改善も後戻り防止に繋がります。定期的な検診を受けることで、後戻りの兆候を早期に発見し、適切な対応をすることができます。
日常生活での注意点
小児矯正中は、装置の破損や虫歯のリスクが高まります。食事には特に注意が必要で、キャラメルやガムなどの粘着性の高い食べ物、固い食べ物(せんべい、フランスパン、氷など)は装置を破損する可能性があるため、控えるようにしましょう。また、歯磨きも丁寧に行う必要があります。装置が付いているため、歯ブラシが届きにくい部分があり、虫歯になりやすいためです。矯正装置専用の歯ブラシや歯間ブラシ、デンタルフロスなどを使い、丁寧に歯磨きをするように指導しましょう。さらに、スポーツをする際には、マウスガードを装着することで、装置の破損や口内へのケガを予防することができます。マウスピース型矯正装置を使用している場合は、スポーツ中は装置を外すように指示される場合もあります。矯正歯科医の指示に従いましょう。
| 注意点 | 詳細 |
|---|---|
| 食事 |
粘着性の高い食べ物や固い食べ物は装置の破損に繋がるため、避ける。 |
| 歯磨き | 装置が付いているため、虫歯になりやすい。矯正装置専用の歯ブラシや歯間ブラシ、デンタルフロスなどを使い、丁寧に歯磨きをする。 |
| スポーツ | マウスガードを装着することで、装置の破損や口内へのケガを予防する。 |
| 保定 | リテーナーの装着は後戻りを防ぐために非常に重要。 |
| 定期検診 | 後戻りの兆候を早期に発見し、適切な対応をするために必要。 |
これらの注意点を守り、矯正歯科医としっかり連携を取りながら治療を進めることで、小児矯正を成功に導くことができます。気になることや不安なことがあれば、遠慮なく矯正歯科医に相談しましょう。
小児矯正に関するよくある質問
ここでは、小児矯正に関するよくある質問と回答をまとめました。
何歳から始められますか?
小児矯正を始めるのに最適な年齢は、お子様の歯並びの状態や顎の成長具合によって異なります。一般的には、顎の成長を利用しやすい6歳から12歳頃が適していると言われています。ただし、指しゃぶりや舌癖などの悪習癖がある場合は、より早期の介入が推奨されることもあります。3歳くらいから相談できる矯正歯科医院もありますので、気になることがあれば早めに相談してみましょう。
痛みはありますか?
小児矯正における痛みは、使用する装置やお子様の感受性によって異なります。床矯正やマウスピース型矯正装置は、比較的痛みを感じにくいと言われています。一方、ブラケット矯正では、ワイヤーの調整後に一時的な痛みや違和感を感じる場合があります。しかし、耐えられないほどの痛みではないことがほとんどで、痛み止めが必要になるケースは稀です。心配な場合は、担当医に相談しましょう。
治療期間はどのくらいですか?
小児矯正の治療期間は、歯並びの状態や治療方法、顎の成長具合によって大きく異なります。一般的には、1年から3年程度かかることが多いです。症例によっては、さらに長期間かかる場合もあります。治療期間については、精密検査の結果に基づいて担当医から説明があります。
費用はどのくらいかかりますか?
小児矯正の費用は、使用する装置や治療期間、医療機関によって異なります。目安として、20万円から80万円程度が相場です。費用については、事前に医療機関に見積もりを依頼し、しっかりと確認することが重要です。
| 矯正装置の種類 | 費用相場 |
|---|---|
| 床矯正 | 20~40万円程度 |
| マウスピース型矯正装置 | 40~80万円程度 |
| ブラケット矯正 | 50~80万円程度 |
詳しくは日本歯科医師会のウェブサイトも参考にしてください。
保険は適用されますか?
小児矯正は、原則として健康保険は適用されません。ただし、顎変形症など、特定の症状に限り保険適用となる場合があります。また、医療費控除の対象となる場合がありますので、確定申告の際に領収書を保管しておきましょう。詳しくは国税庁のウェブサイトをご確認ください。
小児矯正中の食事について
小児矯正中は、装置の種類によっては食事に制限がかかる場合があります。特に、ブラケット矯正の場合は、粘着性の高い食べ物や硬い食べ物は装置が外れたり破損したりする原因となるため、注意が必要です。具体的な食事制限については、担当医から指示がありますので、それに従いましょう。
矯正装置の清掃について
小児矯正中は、矯正装置の清掃を適切に行うことが非常に重要です。装置に食べカスなどが付着したまま放置すると、虫歯や歯周病のリスクが高まります。専用の歯ブラシや歯間ブラシなどを使い、丁寧に清掃しましょう。清掃方法については、担当医から指導があります。
学校生活への影響は?
小児矯正は、学校生活に大きな影響を与えることはほとんどありません。ただし、ブラケット矯正の場合は、発音がしづらくなったり、口内炎ができやすくなったりすることがあります。また、体育の授業などで激しい運動をする際には、マウスガードの着用が必要となる場合があります。気になることがあれば、担任の先生や担当医に相談しましょう。
後戻りについて
小児矯正後、後戻りが起こる可能性はあります。後戻りを防ぐためには、保定装置を指示通りに装着することが重要です。保定期間は、一般的に矯正治療と同じくらいの期間が必要です。担当医の指示に従い、定期的な検診を受けましょう。
まとめ
この記事では、小児矯正が本当に意味がないケース、効果的なケース、メリット・デメリット、種類や注意点などを解説しました。
結論として、小児矯正は顎の成長を利用して歯並びや噛み合わせを改善する効果的な治療法ですが、全ての人に必要というわけではありません。軽度の歯列不正や顎の成長によって自然改善が見込まれる場合は、必ずしも必要ではないでしょう。
しかし、顎の成長に問題があったり、重度の歯列不正がある場合は、小児矯正を行うことで将来的な抜歯や大がかりな矯正治療を回避できる可能性が高まります。また、指しゃぶりなどの悪習慣を改善するのにも有効です。
小児矯正は子どもの成長段階に合わせて治療計画を立てる必要があり、治療期間も長くなる傾向があります。そのため、信頼できる矯正歯科医院を選び、医師とよく相談しながら治療を進めることが大切です。費用や治療期間、子どもの負担などを考慮し、ご自身のお子様に最適な選択をしてください。